やってよかった勉強法|診断士合格までに実践して効果を感じた習慣8選
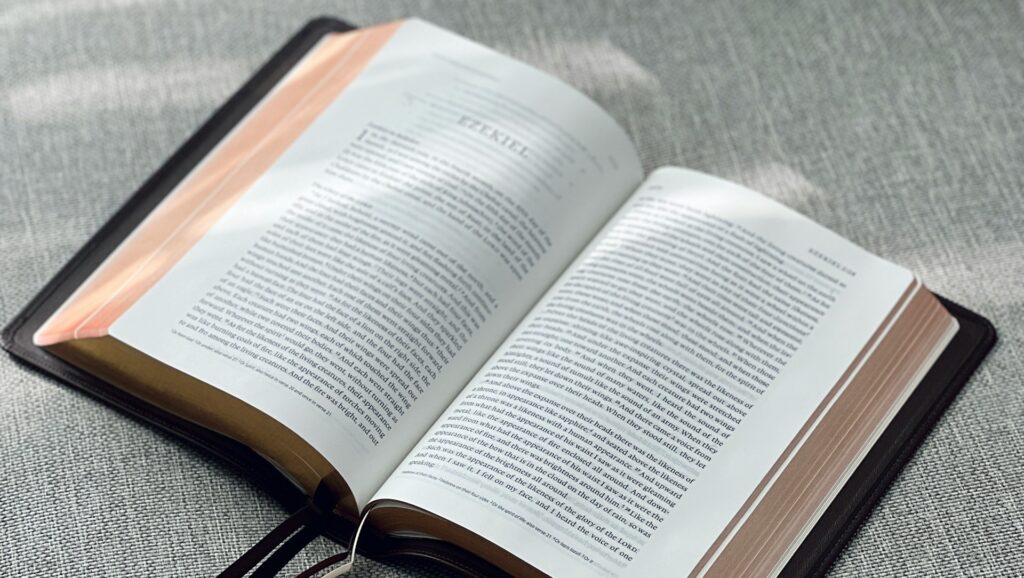
前回の記事「効率的な勉強法|中小企業診断士に合格するための考え方」では、“効率的に学ぶための考え方”についてまとめました。
今回はその続編として、私自身が実際に「やってよかった」と感じた勉強習慣を紹介します。
理屈よりも実体験に基づいた“地味だけど効く方法”ばかりです。
1. テキストは「開けっ放し」が基本
勉強を始めるときに意外と脳のエネルギーを使うのが、“教材を開く”という最初の一歩です。
とある本で「人は『始める』瞬間にも脳の体力を消耗する」と読み、実際に試してみたところかなり効果がありました。
テキストは常に机の上に開けた状態で置いておく。
→ 「よし、やるか」と気合を入れずとも、自然と再開できるようになります。
これは一種の“心理的ハードルを下げる仕掛け”です。
脳の体力を「始めること」ではなく、「理解すること」に使う。地味ですが効果があったと感じています。
2. 昼寝で“午後の集中切れ”を防ぐ
午後になると眠気が出てきて、「勉強しなきゃ」というストレスが倍増しますよね。
私は思い切って昼寝を“勉強計画の一部”に組み込みました。
ただし、午前の方が集中力は高いので、
「やりたいことの7割は午前中に入れる」ことを意識。
昼寝は20〜30分と決めて、リフレッシュの範囲で留めていました。
1時間以上寝ると逆にだるくなることが多かったので、
“短時間リセット”がちょうどよかったです。
3. 「ひとり言」で記憶を定着させる
理解が進まないとき、黙読よりも声に出して説明してみると不思議と理解が進みます。
まるで人に教えているように話すことで、脳が整理されるんです。
たとえば、「財務会計の減価償却とは〜」と自分で語る。
口に出すことで、暗記にもなりやすい。
個室限定の方法ではありますが、記憶の定着にいい方法だと感じました。
4. 机の配置で集中力が変わる
これは人によるかもしれないですが、私にとっては必要なことでした。
私は「椅子の背を壁につける」スタイルに変えたら、一気に集中できるように。
背中側が空いていると落ち着かず、つい後ろを気にしてしまうタイプなんです。
また机の配置を変えるだけで“新しい気持ち”になり、勉強のやる気が湧くのを感じました。
自分の部屋を最も勉強に適した部屋に変えることができたのは、診断士合格に不可欠なことだったと思います。
5. 「自分のペース」でできる通信教育が最適だった
学生時代から「集団授業が苦手」でした。
理解が遅い分、じっくり考える時間を確保すれば、最終的に追いつけるタイプでした。
だから診断士の勉強も、通信教育(診断士ゼミナール)がぴったりでした。
自分のペースで学べるし、何度も動画を見返せる。
決まった時間に拘束されないのは、社会人にとって本当にありがたい仕組みです。
🎓 診断士ゼミナールは、教材の質・解説のわかりやすさ・コスパの三拍子が揃っている
私の中では「社会人が合格を狙うならオススメしたい」講座です。
6. スケジュールは“ざっくり決めて柔軟に修正”
私は最初に全体の勉強スケジュールを大まかに作っていました。
「1年で合格するためには、今どこにいるか」を可視化するためです。
ただ、予定通りに進むことはほぼありません。
進捗に応じて“週単位で微修正”を繰り返しました。
計画は守るためではなく、“軌道修正するための目安”と捉えると、精神的にもラクになります。
7. 心の余裕がないときは無理にやらない
焦って机に向かっても、内容が頭に入らないことは多いです。
そんなときは思い切って休む勇気も必要です。
「今日はやらない」と決めることも、実は“継続の一部”。
無理に頑張らず、“続けること”に価値を置いた方が結果的に長く続きます。
8. 「必勝パターン」を自分なりに作る
資格試験には、「勝ち筋」が存在すると思います。
私の場合はこの流れが最も効率的でした。
- 映像講義で全体像をつかむ
- テキストを熟読して理解を固める
- ひたすら過去問演習でパターンを体に染み込ませる
過去問を通して、出題傾向・論点のつながり・自分の弱点がすべて見えてきます。
「勝ち筋」に乗れると勉強期間中や試験本番でも自身になります。
まとめ:小さな工夫の積み重ねが合格を作る
どれも特別なことではありません。
でも、“続けられる仕組み”を整えることで、合格への距離が確実に近づきます。
無理せず・マイペースに・でも諦めない。
それが「中小企業診断士」合格に向けて、私が伝えたい勉強スタイルです。
関連記事:中小企業診断士一次試験の勉強時間はどれくらい?500時間で一発合格した体験談
関連記事:中小企業診断士試験、私が一発合格できた教材はこれだけだった

