中小企業診断士合格に役立った!やらなくてよかった勉強法
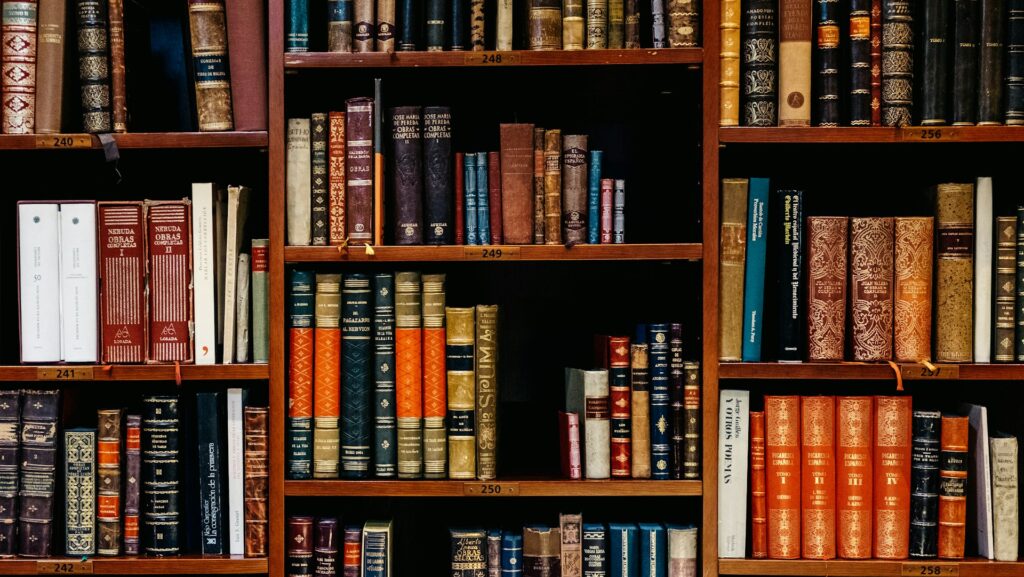
ほとんどの方は学生時代からの我流で勉強していることが多いと思いますが、実は非効率的なやり方を続けてしまっているケースも少なくありません。
私は中小企業診断士の勉強をしていたとき、勉強法に工夫を加えていました。
ここでは、メンタリストDaiGoさんの著書『最短の時間で最大の成果を手に入れる 超効率勉強法』の中から、私が実際に「やらなくてよかった」と感じた勉強法を紹介します。
ハイライト・アンダーライン
テキストの重要部分にマーカーを引く人は多いと思います。ですが、丁寧に線を引こうとすると時間ばかりかかり、気づけばあちこち線だらけで「どこが本当に重要なのか分からない…」という状態になりがちです。
実際、本でも「線を引いた段階では重要な情報を選別しただけで、その内容を覚える価値があるとまでは考えておらず、勉強の中身は頭に定着はしない」と指摘されています。
私自身も同じように悩んだ経験がありました。そこで思い切ってやり方を変え、シャーペンでざっくり線を引いたり丸をつける程度にし、本当に大事だと思った部分だけ赤ペンで強調する方法に切り替えました。結果として重要箇所がシンプルに浮き上がり、見返したときに学習効率が上がったと感じています。
また、線を丁寧に引くことに執着しなくなり、私が勉強で一番大事にしている「問題をひたすら解く」ことに集中できるようになりました。
テキストの要約
テキストを要約するのは、一見すると理解が深まりそうに思えます。ですが、まとめ作業に時間をかけすぎると「まとめたこと」に満足してしまい、肝心の理解や記憶が深まらないケースが多いのではないでしょうか。さらに要約の構成を考えるのも手間がかかり、私自身は「非常に無駄な時間を過ごしている」と感じました。
本では、要約という行為はそもそも「難易度が高い」く、また要約が得意な人は適切な情報を整理できているため、「要約がうまい人ほど要約は不要」だと指摘されています。
実際、私は要約にかける時間を思い切ってなくし、その分を「一番大事な問題をひたすら解く時間」にあてるようにしました。その方が理解の定着に直結し、効率も格段に上がったと思います。
テキストの再読
テキストを毎日読み返している方も多いと思います。しかし、同じ箇所を繰り返し読むだけでは内容が頭に残りにくく、私自身も「効果は限定的だな」と感じていました。理解を深めたいときに必要な部分へ戻って読む程度で十分だったと思います。
本でも「再読は受け身の勉強法になりやすい」と指摘されています。そもそも人間の脳は、興味を持てない情報を効率的に取り込めないようにできているため、ボーッと本を読んでいるとページ数だけは進んでも、内容がまったく頭に残らないという体験をする人は多いはずです。
私の場合も同じで、ただ再読を繰り返すよりも、問題演習を通して「なぜそうなるのか」を考える方が圧倒的に記憶に残りました。
まとめ
資格勉強では「やるべきこと」を増やすよりも、むしろ「やらなくていいこと」を見極めることが大切です。ハイライト、要約、再読といった一見王道に見える勉強法も、私には効率が悪く、思い切ってやめて正解でした。
次の記事では、逆に「やってよかった勉強法」について紹介します。効率的に合格へ近づくためのヒントになると思いますので、ぜひ併せてご覧ください。

